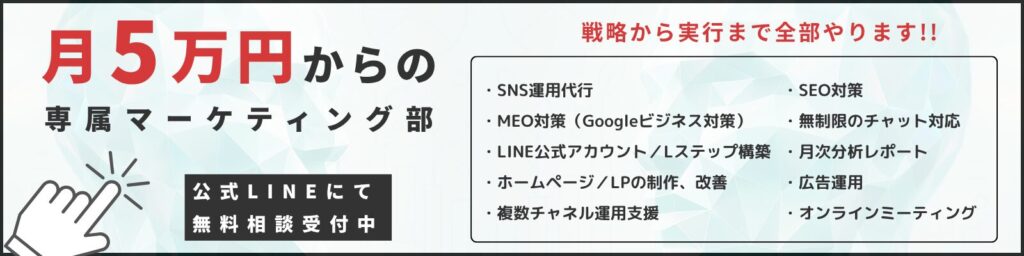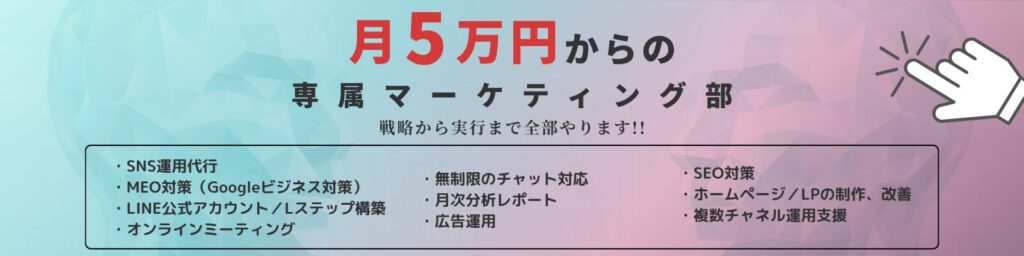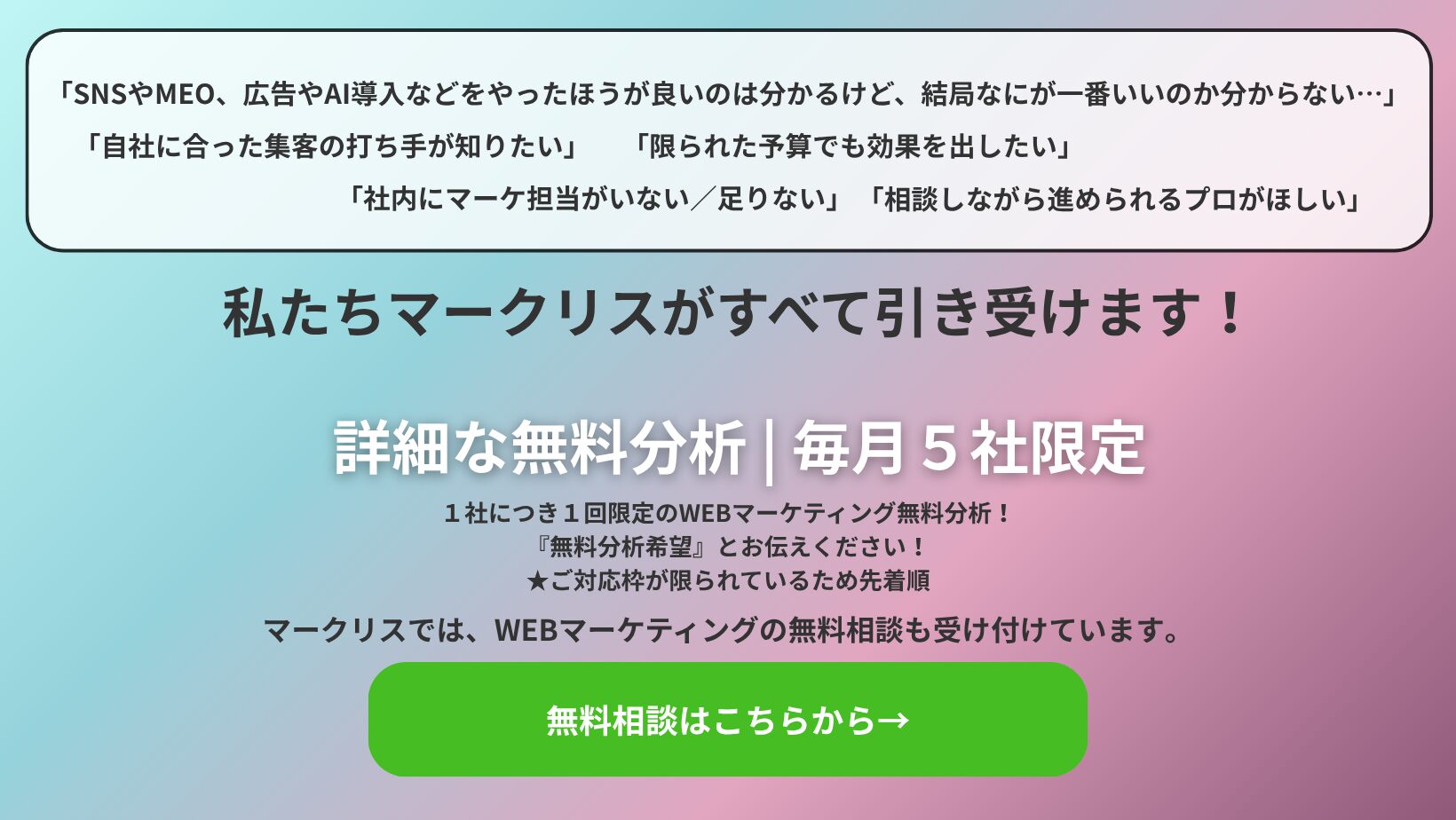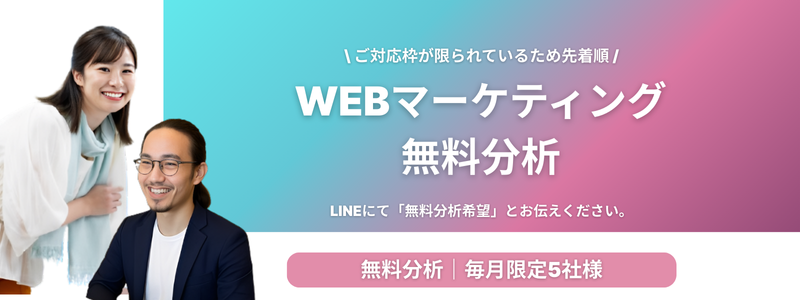「マーケティングって難しそう…でもやらなきゃいけないのはわかっている」
「紹介やチラシだけでは限界を感じている…」
「何から始めればいいのか分からない…」
こうした悩みを抱えている工務店経営者の方は、本当に多いのではないでしょうか。
実際に私も多くの工務店の皆さんとお話しする中で、「マーケティングの必要性は感じているけれど、どこから手をつければいいのか分からない」「専門的すぎて自分たちには無理そう」という声をよく聞きます。
確かに、マーケティングと聞くと難しい専門用語や複雑な手法をイメージしがちです。しかし、工務店にとってのマーケティングは、実はそれほど複雑ではありません。お客様に「選ばれる理由」を明確にし、それを適切に伝える仕組みを作ることが、工務店マーケティングの本質なのです。
この記事では、工務店が初めてマーケティングに取り組むための考え方・手順・具体的な施策を、初心者の方にも分かりやすく解説します。難しい理論は抜きにして、明日からでも実践できる内容に絞ってお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
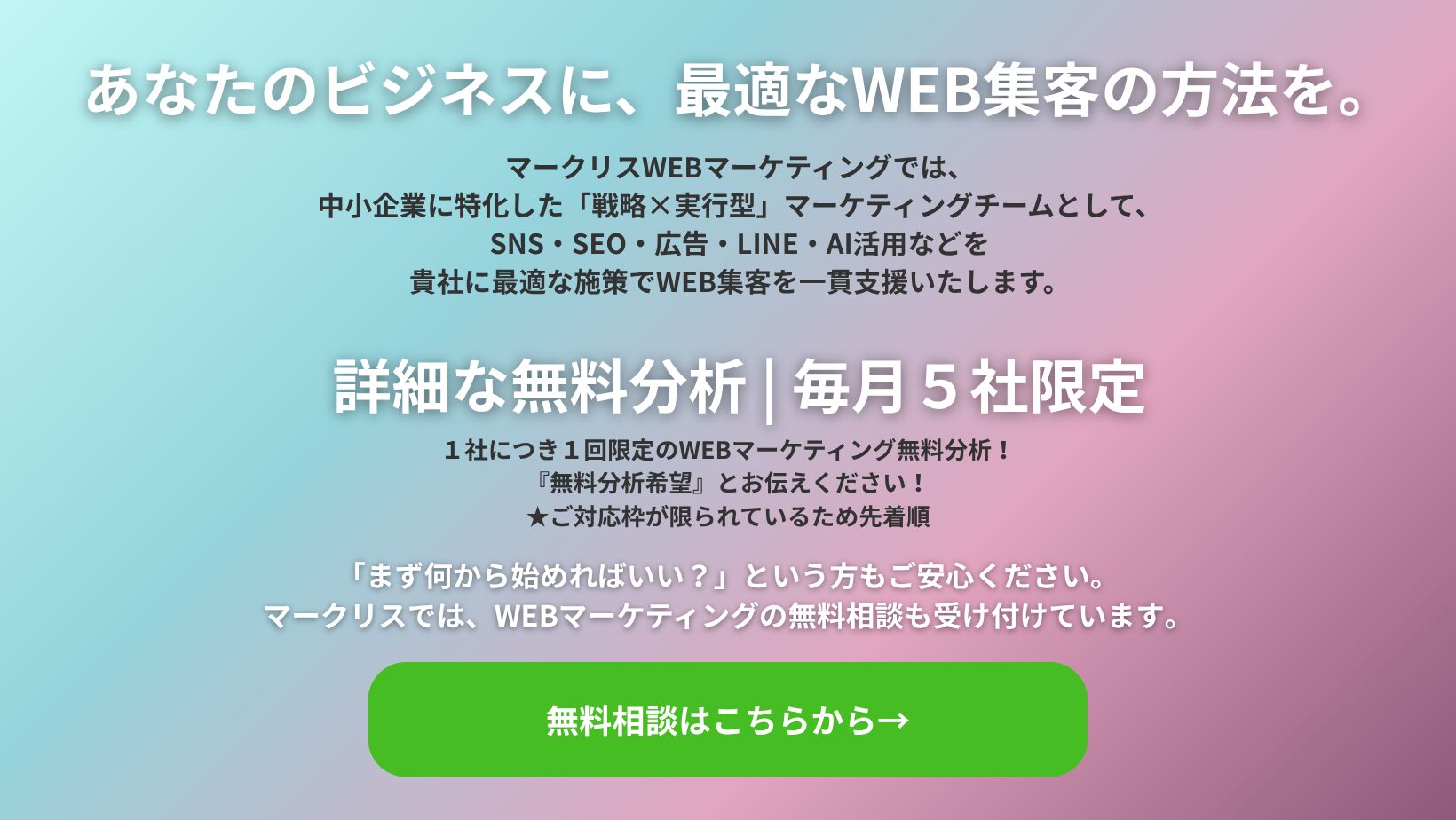
そもそもマーケティングとは?【初心者向け解説】
まず、マーケティングという言葉の意味を、工務店の文脈で分かりやすく整理しましょう。
多くの経営者が持つ「マーケティング=難しいもの」という先入観を取り除くことが、成功への第一歩です。
「営業」との違いとは?
工務店では「営業」という言葉には馴染みがあっても、「マーケティング」はピンとこない方が多いかもしれません。この2つの違いを理解することで、マーケティングの重要性が見えてきます。
営業は、既に関心を持っているお客様に対して、具体的な提案を行い、契約を獲得する活動です。
例えば、見学会に来場されたお客様への商談や、問い合わせをいただいたお客様への提案などがこれにあたります。
一方、マーケティングは、まだ自社を知らない人や、家づくりを漠然と考えている人に対して、関心を持ってもらう活動です。SNSでの施工事例発信、ブログでの家づくりノウハウ提供、見学会の集客などがマーケティング活動になります。
分かりやすい例:魚釣りに例えると、マーケティングは「魚が集まる場所を見つけ、良い餌を用意すること」、営業は「実際に釣り針を垂らして魚を釣り上げること」です。どちらも重要ですが、まず魚が集まらなければ釣ることはできません。
工務店にとってのマーケティングとは「選ばれる仕組みづくり」
工務店の場合、お客様にとって住宅は人生最大の買い物です。慎重に検討を重ね、複数の会社を比較検討します。
その中で「この工務店に任せたい」と思ってもらうためには、単に良い仕事をするだけでは不十分です。
なぜ自社を選ぶべきなのか、その理由を明確にし、適切な方法でお客様に伝えることが、工務店のマーケティングです。
これは決して小手先のテクニックではなく、お客様との信頼関係を築くための本質的な活動なのです。
選ばれる理由には、以下のような要素があります:
- 技術力・施工品質:「確かな技術で安心の住まいを提供」
- デザイン性:「お客様の理想を形にするデザイン力」
- コストパフォーマンス:「適正価格で最大の価値を提供」
- アフターサービス:「建てた後も安心の長期サポート」
- 地域密着:「地域を知り尽くした安心感」
- 人柄・信頼性:「親身になって相談に乗ってくれる」
「集客→信頼→成約→紹介」の流れをつくることが目的
工務店のマーケティングの最終目的は、「集客→信頼→成約→紹介」という好循環を作り出すことです。この流れが確立されれば、安定した事業成長が可能になります。
集客:SNSやホームページを通じて、自社の存在を知ってもらう
信頼:施工事例や お客様の声を通じて、技術力や人柄を理解してもらう
成約:信頼関係が築けたお客様と契約を結ぶ
紹介:満足したお客様が、知人に自社を紹介してくれる
この循環の中で、紹介によって新たな見込み客が生まれ、再び集客段階に戻ることで、持続的な成長が実現されます。マーケティングは、この循環を効率的に回すための仕組みづくりなのです。
https://marklis.com/koumuten-meo-seo/

工務店におけるマーケティングの全体像
それでは、お客様が工務店を知ってから契約に至るまでの過程を、5つの段階に分けて詳しく見ていきましょう。
各段階で必要なマーケティング活動を理解することで、何をすべきかが明確になります。
① 認知:まずは「知ってもらう」
マーケティングの第一段階は、地域のお客様に自社の存在を知ってもらうことです。
どんなに良い工務店でも、存在を知られていなければ選択肢に入ることすらできません。
認知獲得の主な手法:
- Googleマップ(MEO):「○○市 工務店」で検索された際に上位表示
- Instagram:地域のハッシュタグや施工事例の投稿
- ホームページのSEO:検索エンジンからの自然な流入
- チラシ・看板:従来手法も地域密着では有効
- 口コミ・紹介:既存客からの自然な拡散
重要なのは、お客様が情報収集する場所に適切に存在することです。現代では、多くのお客様がインターネットで最初の情報収集を行うため、オンラインでの認知獲得は特に重要になっています。
② 興味・共感:SNS・ブログで”人柄”と”実績”を伝える
存在を知ってもらった次は、「この工務店、良さそうだな」と興味を持ってもらう段階です。ここでは、技術力だけでなく、工務店の「人柄」や「価値観」を伝えることが重要になります。
住宅は高額で長期間に渡るお付き合いになるため、お客様は「この人たちなら信頼できる」と感じられる工務店を選びたいと考えています。単なる宣伝ではなく、日常的な発信を通じて人柄を伝えることが効果的です。
興味・共感を得るためのコンテンツ例:
- 施工事例の詳細紹介:ビフォー・アフターと工夫したポイント
- 職人の仕事風景:丁寧な作業への取り組み姿勢
- お客様との打ち合わせ風景:親身な相談対応の様子
- 地域への貢献活動:清掃活動や地域イベント参加
- 家づくりのノウハウ:専門知識を分かりやすく解説
③ 接点:LINE・見学会・資料請求で関係づくり
興味を持ったお客様との具体的な接点を作る段階です。ここで重要なのは、お客様が「相談しやすい」「情報を得やすい」環境を整備することです。
現代のお客様は、いきなり電話で問い合わせることに抵抗を感じる方が多いため、気軽にアクセスできる接点を用意することが重要です。
効果的な接点の例:
・LINE公式アカウント:気軽にメッセージで相談可能
・資料請求フォーム:まずは情報収集から始められる
・見学会予約:実際の住宅を体感できる
・オンライン相談:自宅から気軽に参加可能
④ 成約:強みと安心感を伝えてクロージング
接点を持ったお客様との信頼関係を深め、最終的な契約につなげる段階です。ここでは、他社との差別化ポイントと、お客様の不安を解消する情報提供が重要になります。
お客様が契約を決める際の判断要素:
- 技術力・品質:施工実績や使用材料の説明
- 価格の妥当性:コストの内訳と他社比較
- アフターサービス:保証内容とメンテナンス体制
- 完成時期:工期の明確化と進捗管理
- 担当者との相性:コミュニケーションの取りやすさ
この段階では、お客様の不安や疑問に対して誠実に答えることが最も重要です。無理な営業を行うよりも、お客様に安心して決断していただけるよう、十分な情報提供に努めることが結果的に成約率向上につながります。
⑤ リピート・紹介:OB対応や定期フォロー
契約・引き渡しで終わりではありません。引き渡し後のフォローこそが、次の集客につながる重要なマーケティング活動です。満足したお客様は、最高の営業担当になってくれるからです。
リピート・紹介を生み出すフォロー活動:
- 定期点検・メンテナンス:住み始めた後の安心サポート
- 季節の挨拶・情報提供:継続的な関係維持
- リフォーム提案:ライフステージ変化への対応
- 紹介特典:紹介しやすい環境の整備
- OB施主イベント:交流を通じた関係深化
建てた後も大切にしてくれる工務店という印象を与えることで、お客様は安心して知人に紹介してくれるようになります。この紹介が新たな集客の源泉となり、マーケティングの好循環が生まれるのです。
初心者でも実践できる!工務店のマーケティング手法7選
ここからは、マーケティング初心者の工務店でも今すぐ始められる、具体的な手法を7つご紹介します。すべてを一度に始める必要はありません。自社の状況に合わせて、できるものから順番に取り組んでいきましょう。
① ホームページの見直しと導線整理
すべてのマーケティング活動の「受け皿」となるのがホームページです。SNSや広告でどんなに集客しても、ホームページが整備されていなければ、せっかくの見込み客を逃してしまいます。
スマホ対応・施工事例・LINE誘導が3大ポイント
現在、ホームページへのアクセスの70%以上がスマートフォンからです。スマホで見やすく、操作しやすいホームページになっているかを最初にチェックしましょう。
ホームページで重視すべき3つの要素:
- スマホ対応:画面サイズに合わせた表示、読みやすい文字サイズ、タップしやすいボタン
- 施工事例:写真付きの詳細な事例紹介、価格帯別や家族構成別の分類
- LINE誘導:気軽に相談できるLINE公式アカウントへの導線
特に重要なのは、訪問者が「次に何をすればいいか」が明確に分かる導線設計です。「資料請求」「LINE登録」「見学会予約」など、訪問者の検討段階に応じた複数の選択肢を用意することが効果的です。
② Googleマップ(MEO)の最適化
地域密着の工務店にとって、MEO(Map Engine Optimization)対策は最重要課題の一つです。「○○市 工務店」で検索された際に、Googleマップの上位に表示されることで、地域のお客様からの認知度が格段に向上します。
口コミ・投稿・カテゴリ設定で検索に強くなる
MEO対策の基本は、Googleビジネスプロフィールの最適化です。以下の3つの要素を重点的に取り組みましょう:
- 口コミ獲得:お客様からの口コミを積極的に集める
- 定期投稿:施工事例や見学会情報を週2〜3回投稿
- カテゴリ設定:「工務店」「注文住宅業者」「リフォーム業者」など関連カテゴリを設定
MEO対策のコツ:投稿内容には必ず地域名を含める(「○○市での施工事例」「○○町の見学会開催」など)ことで、地域検索での露出率が高まります。また、お客様からの口コミには必ず返信することで、Googleからの評価も向上します。
③ Instagramの施工事例発信
Instagram は、視覚的な魅力を伝えやすい住宅業界には非常に相性の良いプラットフォームです。特に30〜40代の家づくり世代の利用率が高く、工務店の重要なターゲット層にリーチできます。
地域×共感×人柄がカギ/ストーリーズ・ハイライト活用
Instagram で成功するためのポイントは、単なる宣伝ではなく、共感を生むコンテンツを発信することです。
効果的なInstagram投稿の内容:
- 施工事例:ビフォー・アフター、こだわりポイントの詳細
- 作業風景:職人の丁寧な仕事ぶり、現場の様子
- お客様との打ち合わせ:親身な相談対応の様子
- 社員の日常:人柄が伝わる自然な投稿
- 地域情報:おすすめスポットや地域イベント
ストーリーズ機能は、より日常的で親しみやすいコンテンツを発信するのに適しています。完成度の高い投稿は通常の投稿で、リアルタイムな情報はストーリーズで使い分けることで、フォロワーとの距離感を縮めることができます。
④ ブログ・コラムで見込み客の悩みを解決
ホームページ内にブログやコラムページを設け、家づくりを検討中のお客様の悩みや疑問に答えるコンテンツを発信しましょう。これにより、検索エンジンからの流入も期待でき、長期的な集客効果が見込めます。
「土地の選び方」「坪単価の考え方」などを記事化
お客様が家づくりで抱く疑問は、ある程度パターン化されています。これらの疑問に対して、専門家の視点から分かりやすく解説することで、お客様にとって価値のあるコンテンツを提供できます。
人気の高いブログテーマ例:
- 土地選びのポイント:立地条件、地盤、法規制などの解説
- 予算の考え方:坪単価の仕組み、諸費用の内訳
- 間取りのアイデア:家族構成別のおすすめプラン
- 住宅ローンの基礎知識:金利タイプ、返済方法の比較
- 季節別のメンテナンス:住宅の長期維持のポイント
重要なのは、売り込み色を抑えて、純粋にお客様の役に立つ情報を提供することです。有益な情報を提供することで信頼関係が構築され、実際に検討段階になった際に相談先として選ばれやすくなります。
⑤ LINE公式アカウントの開設と活用
現代のお客様にとって、LINEは最も身近なコミュニケーションツールです。電話での問い合わせに抵抗を感じる方でも、LINEであれば気軽にメッセージを送ることができます。
資料請求・イベント案内・定期接触に使える
LINE公式アカウントの活用方法は多岐にわたります:
- 個別相談:家づくりに関する質問に随時対応
- 資料配信:施工事例集や間取りプランのPDF送信
- イベント案内:見学会や相談会の優先案内
- 定期情報配信:家づくりお役立ち情報の提供
- 予約受付:見学会や個別相談の予約システム
LINE活用のコツ:リッチメニューを設定して「施工事例」「資料請求」「見学会予約」「個別相談」などのボタンを配置することで、お客様が求めている情報にすぐにアクセスできる環境を整えましょう。
⑥ 見学会・相談会などリアルとの連動
デジタルマーケティングが重要とはいえ、住宅は実際に見て、触れて、体感することが重要な商材です。オンラインでの集客活動と、リアルでの体験機会を効果的に連動させることが成功の鍵となります。
SNSやLINEからオフラインイベントへ誘導
オンラインとオフラインの連動例:
- 完成見学会:Instagram で事前に内装をチラ見せ、当日の詳細体験へ誘導
- 構造見学会:ブログで構造の重要性を解説、実際の構造を見学
- 資金計画セミナー:LINE で事前に資料配布、セミナーで詳細解説
- 土地探し相談会:ホームページで地域情報を紹介、個別相談で具体的提案
オンラインで興味を持ったお客様が、自然にオフラインイベントに参加したくなるような導線設計が重要です。事前情報の提供により、参加者の関心度も高まり、より質の高い商談につながります。
⑦ 顧客の声(口コミ・インタビュー)を活用
どんなに自社で「良い工務店です」と言うよりも、実際のお客様からの声の方が圧倒的に信頼性が高く、説得力があります。お客様の声を積極的に収集し、マーケティング活動に活用しましょう。
施工後のお客様の声をSNS・HPに展開
お客様の声を活用する方法:
- 写真付きアンケート:完成住宅とお客様の笑顔
- 動画インタビュー:より臨場感のある体験談
- 手書きの感想文:温かみのあるリアルな声
- Before・After体験談:家づくりの過程から完成まで
- 住み始めてからの感想:実際の住み心地レポート
お客様の声を掲載する際は、必ず事前に許可を得ることが重要です。また、良い点だけでなく、改善点や要望も含めて紹介することで、より信頼性の高いコンテンツになります。

初心者がやりがちな失敗とその対策
マーケティング初心者の工務店がよく陥りがちな失敗パターンと、その対策について解説します。
これらの失敗を避けることで、効率的にマーケティング活動を進めることができます。
全部いっぺんに始めようとする → 優先順位をつける
「ホームページもSNSもブログもLINEも…」と、すべてを同時に始めようとして、結果的にどれも中途半端になってしまうケースが非常に多く見られます。
対策:現状と目標を整理し、優先順位を明確にする
- 第1優先:ホームページの整備(すべての活動の受け皿)
- 第2優先:MEO対策(地域検索での上位表示)
- 第3優先:SNS(Instagram または Facebook)
- 第4優先:LINE公式アカウント
- 第5優先:ブログ・コンテンツマーケティング
一つの施策が軌道に乗ってから次に進むことで、着実に成果を積み上げることができます。
「とりあえずSNS投稿」→誰に届けたいかを決める
「とりあえずInstagramやFacebookを始めよう」と投稿を開始するものの、「誰に」「何を」伝えたいのかが曖昧で、効果的な発信ができないケースです。
対策:ターゲットとメッセージを明確化する
ターゲット設定の例:
・30代夫婦、世帯年収600万円、子ども1〜2人
・現在アパート住まい、初回購入
・予算2000〜2500万円、土地から探している
・自然素材や省エネに関心がある
→この層に響く「自然素材の良さ」「子育て世代の間取り」などを発信
効果測定をしない → GA4やLINE登録数など指標を持つ
マーケティング活動を始めても、「効果が出ているかどうか分からない」「何を改善すべきか分からない」という状況に陥りがちです。
対策:シンプルな指標で効果測定を行う
- ホームページ:月間アクセス数、問い合わせ数
- SNS:フォロワー数、いいね数、コメント数
- LINE:友だち登録数、メッセージ開封率
- MEO:Google マップでの表示回数、クリック数
- 全体:見学会参加者数、資料請求数、契約数
月に1回程度、これらの数値を記録し、前月との変化を確認するだけでも、改善すべき点が見えてきます。
https://marklis.com/koumuten-web-lead-gen/
成果を出すための3つのステップ
最後に、工務店がマーケティングで成果を出すために必要な3つのステップをご紹介します。これらのステップに沿って取り組むことで、効果的なマーケティング活動を展開できます。
① ターゲットを明確に(家族構成・年収・ライフスタイル)
「みんなに愛される工務店」を目指すのではなく、「特定の層から絶対的に支持される工務店」を目指すことが重要です。ターゲットが明確になれば、発信すべきメッセージも自然に決まります。
ターゲット設定で考慮すべき要素:
- 家族構成:新婚夫婦、子育て世代、シニア世代
- 年収・予算:具体的な価格帯でのセグメント
- ライフスタイル:アウトドア好き、在宅ワーク、ペット飼育
- 価値観:自然素材志向、省エネ重視、デザイン重視
- 住まいの状況:初回購入、建て替え、中古リノベ
② 自社の強みを”言語化”する(素材/技術/人柄)
「うちは良い工務店です」では、お客様には伝わりません。何がどのように良いのか、具体的に言語化することが重要です。
強みの言語化例:
- 技術面:「創業50年の伝統技術と最新工法の融合」
- 素材面:「地元産無垢材を活かした自然素材の家」
- デザイン面:「シンプルで飽きのこない、長く愛される住まい」
- サービス面:「建てた後も安心、3世代にわたるお付き合い」
- 人柄面:「家族のような距離感で寄り添う工務店」
これらの強みを、具体的な事例や数値と組み合わせて表現することで、説得力のあるメッセージになります。
③ 小さく始めて継続する(SNS投稿→LINE誘導→相談へ)
マーケティングは継続が命です。最初から完璧を目指すのではなく、小さく始めて改善を重ねながら継続することが成功への道筋です。
継続のためのコツ:
- 無理のないペース:週2〜3回の投稿から始める
- テンプレート化:投稿パターンを決めて効率化
- チーム体制:複数人で役割分担する
- 効果測定:月1回の振り返りで改善点を見つける
- 長期視点:3〜6ヶ月での効果を期待する
「SNS投稿→LINE誘導→相談へ」の基本的な流れを確立し、それを継続的に回すことで、安定した集客の仕組みが構築されます。
よくある質問(Q&A)
工務店のマーケティングについて、よく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 社内にマーケティング担当者がいないのですが大丈夫?
A. はい。最初は代表・事務・広報が兼任で十分です。テンプレートや外部パートナーを使うことで負担を減らせます。多くの成功している工務店も、専任担当者を置かずに効果的なマーケティングを行っています。重要なのは継続することであり、完璧さではありません。投稿テンプレートを作成したり、撮影から投稿まで外部に委託したりすることで、社内の負担を最小限に抑えることができます。
Q2. SNSとホームページ、どちらを優先すべき?
A. 両方大事ですが、まずは“集客の受け皿”であるホームページの整備が先。その後SNSで集客し、導線をつなげましょう。SNSで興味を持ったお客様が、ホームページで詳しい情報を確認できる環境を整えることが重要です。ホームページが整備されていない状態でSNS集客を行っても、せっかくの見込み客を逃してしまう可能性があります。
Q3. 難しい分析や広告運用は必要ですか?
A. 初期は不要です。「LINE登録数」「アクセス数」「問い合わせ数」など、シンプルな数値で十分です。複雑な分析ツールや広告運用は、基本的な施策が軌道に乗ってから検討しても遅くありません。まずは「先月と比べて問い合わせが増えたか」「LINE登録者は増えているか」といった基本的な指標で効果を測定しましょう。
Q4. 小規模な工務店でもマーケティングは必要?
A. むしろ小規模こそ“人柄”や”地域密着”を伝えるマーケティングが必要です。差別化のカギになります。大手ハウスメーカーでは表現できない「社長の顔が見える安心感」「地域に根ざした信頼関係」「きめ細かい対応力」こそが、小規模工務店の最大の武器です。これらの強みを適切に伝えることで、大手では真似できない価値を提供できます。
Q5. すぐに効果は出ますか?
A. 短期施策(MEO・SNS広告)と中長期施策(SEO・LINE)を組み合わせることで、3ヶ月〜6ヶ月で効果が見え始めるのが一般的です。MEO対策やInstagram投稿は比較的早く効果が現れますが、ブログでのSEO効果やLINEでの関係構築には時間がかかります。重要なのは短期的な結果に一喜一憂せず、継続的に取り組むことです。
まとめ|マーケティングは”選ばれるための仕組み”づくり
工務店にとってマーケティングとは、お客様に「選ばれるための仕組み」をつくることです。難しい専門用語や複雑な手法は必要ありません。重要なのは、自社の強みを明確にし、それを適切な方法でお客様に伝え続けることです。
この記事でご紹介した7つの手法は、どれも明日からでも始められる内容です。すべてを一度に始める必要はありません。現在の状況と目標に合わせて、優先順位をつけて取り組んでいきましょう。
- 難しく考えず、できることから1つずつ始めよう
- 工務店ならではの”人”と”地域”を武器に発信
- ホームページ、SNS、LINEを連携させて、見込み客との関係性を育てよう
マーケティングの成果は一朝一夕で現れるものではありません。しかし、継続的に取り組むことで、必ず「選ばれる工務店」へと成長できます。
最も重要なのは、お客様の立場に立って考えることです。「どんな情報があれば安心できるか」「どのような伝え方なら信頼できるか」を常に意識しながら、誠実なマーケティング活動を続けていきましょう。
工務店の皆さんが持つ技術力、人柄、地域への愛情は、必ずお客様に伝わります。その価値を適切に「見える化」することで、地域で最も信頼される工務店を目指していきましょう。