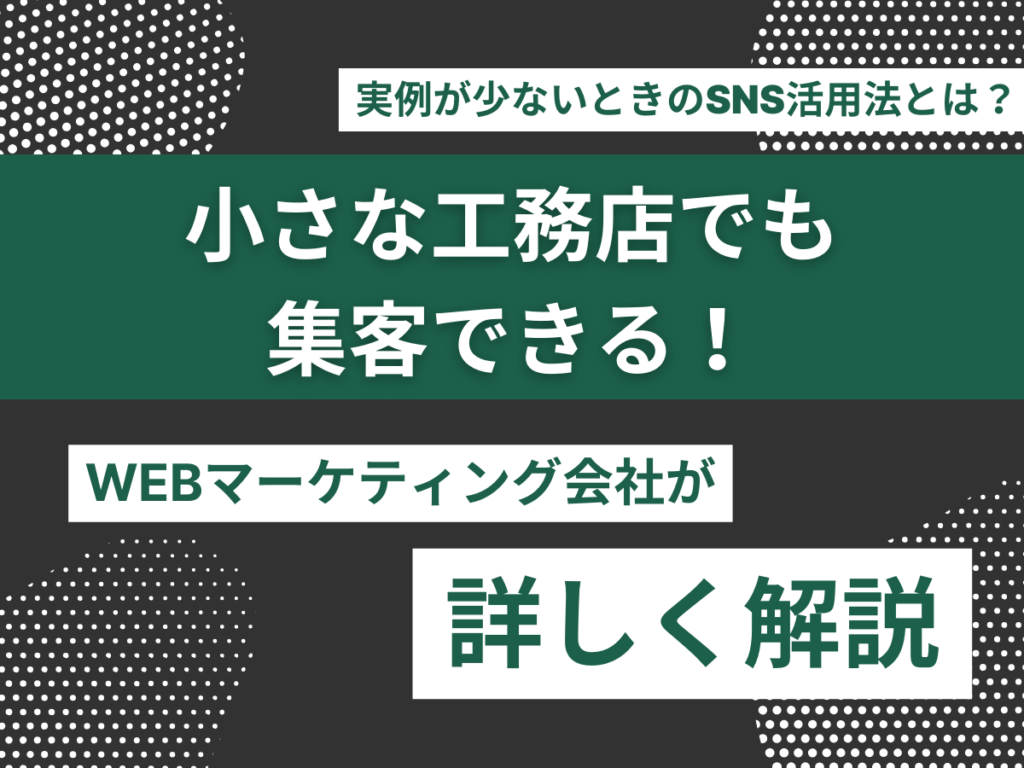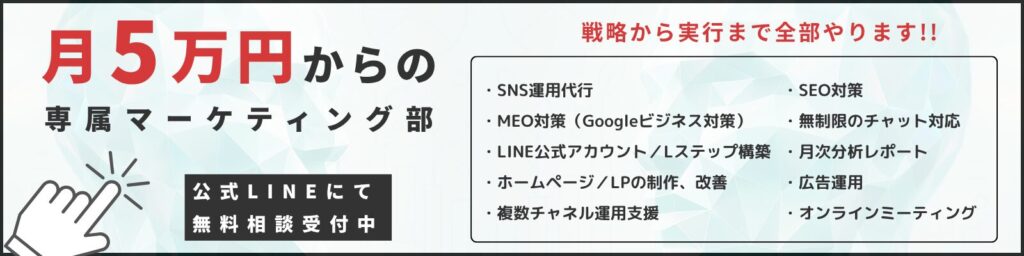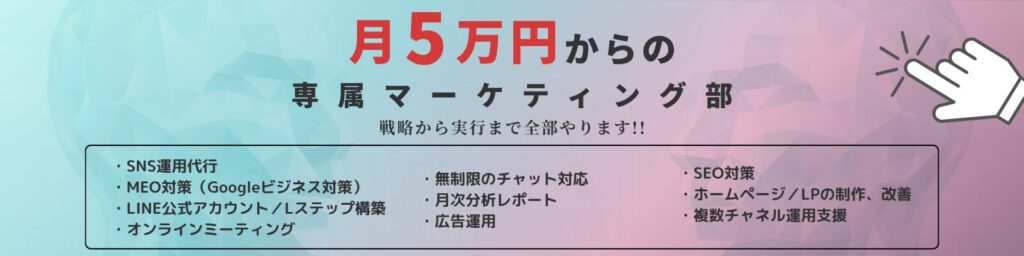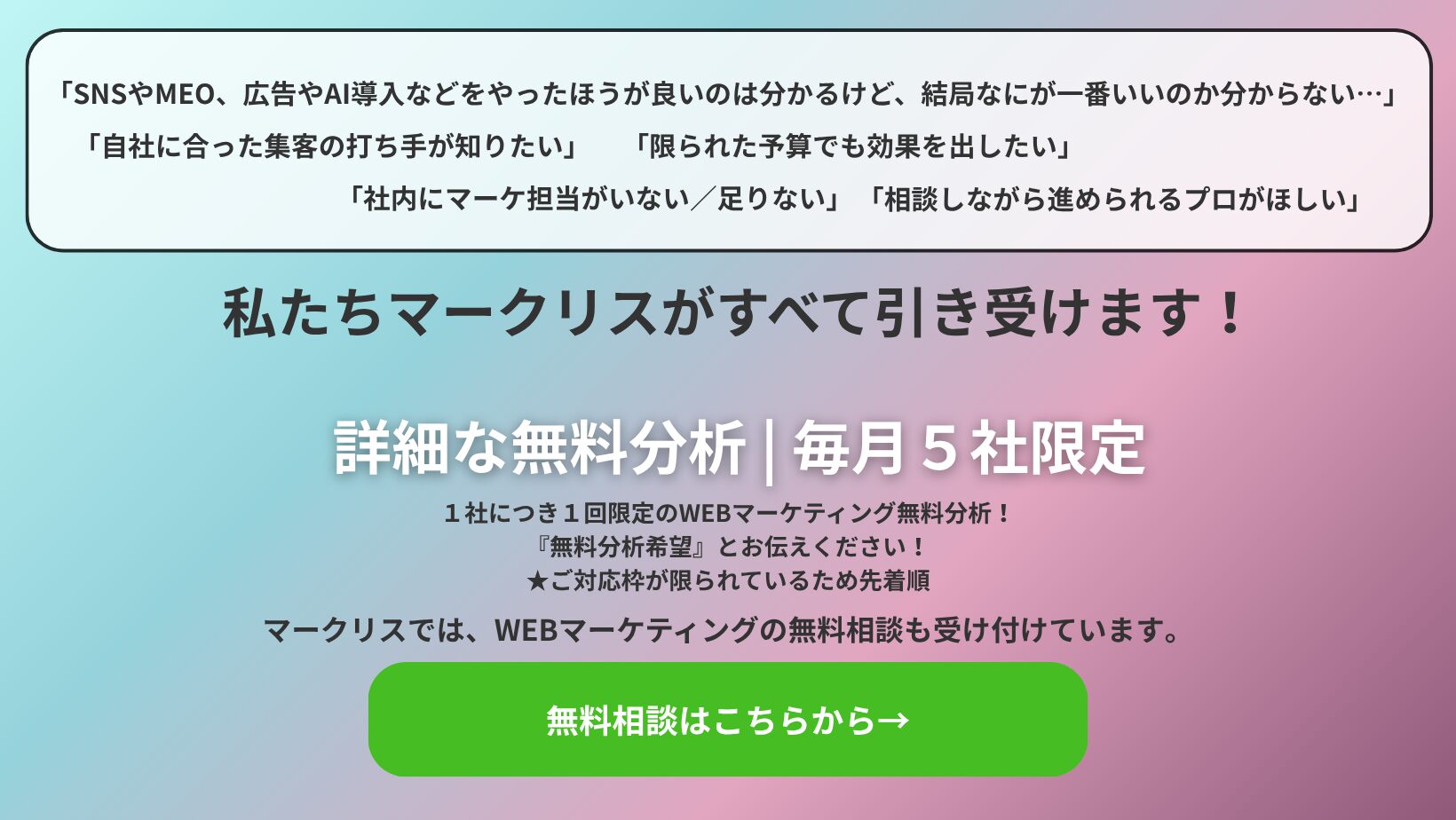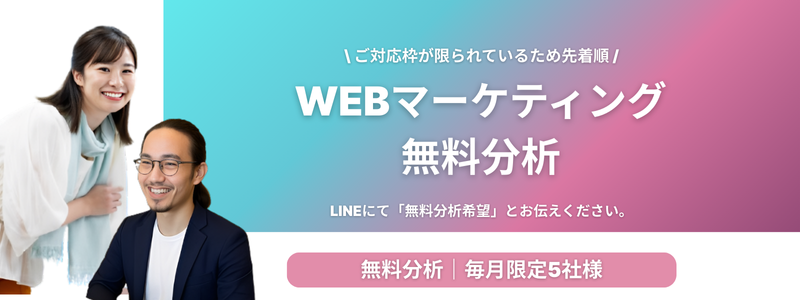「SNSを始めたいけど、施工例が少なくて投稿するネタがない…」
小規模な工務店や創業間もない方なら、同じ悩みを抱えている方も多いはずです。
「自社の施工例が少ないから、SNSで他社に勝てない」と思い込んでしまい、SNS活用を諦めてしまうケースも珍しくありません。
ですが、投稿内容の工夫次第で十分戦えます!実際に、私が知っている工務店では、設立2年目で施工実績が3件しかない状態でも、SNSを通じて月に5〜8件の問い合わせを獲得している事例があります。
この記事では、自社施工例が少なくても「映える投稿」を作り、集客や信頼につなげるための具体的なアイデアと戦略を解説します。施工実績の少なさをハンデと考えるのではなく、むしろ「お客様との距離が近い」「一件一件を大切にしている」というメリットに変換する方法もお伝えしていきます。
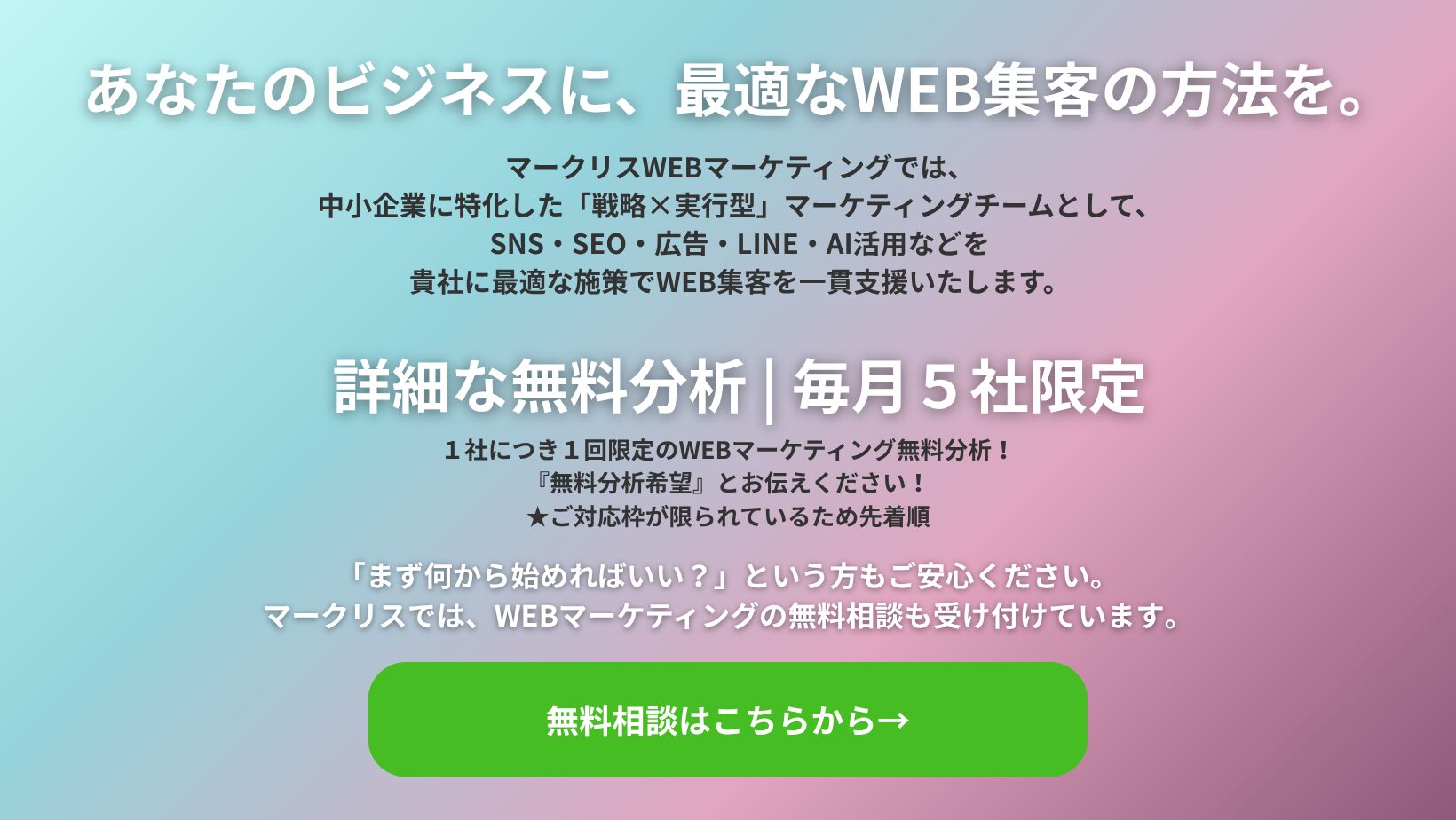
自社施工例が少ない工務店がSNSで成果を出すための考え方
施工例が少ない工務店がSNSで成功するためには、まず考え方を変える必要があります。
多くの工務店が「施工写真がないと投稿できない」と思い込んでいますが、これは大きな誤解です。
「映える」ことより「伝わる」ことが大切
SNSでよく見かける「映える投稿」は確かに注目を集めますが、工務店にとって本当に重要なのは「お客様に自社の魅力が伝わること」です。
例えば、豪華な施工写真を10枚投稿するよりも、たった1枚の写真に「なぜこの素材を選んだのか」「お客様がどんな想いでこの家を建てたいと言われたのか」といったストーリーを添えた方が、見る人の心に響きます。
実際に、ある工務店では施工中の何気ない写真に「お客様のお子さんが『ここが僕の部屋になるんだ!』と嬉しそうに話していました」というコメントを添えただけで、多くの共感コメントが寄せられ、問い合わせにつながったケースもあります。
SNSは”人柄”や”想い”でファンを作るメディア
大手住宅メーカーと比べて、中小工務店の最大の強みは「人と人のつながり」です。SNSは、この強みを最大限に活かせるメディアなのです。
とある地方の小さな工務店では、社長が毎朝の現場巡回の様子を投稿し、「今日も安全第一で頑張ります!」という一言を添えるだけで、地域の方々から「いつも見てます」「安心して任せられそう」といった声をもらっています。
- 代表や職人の人柄
- 家づくりに対する熱い想い
- お客様を大切にする姿勢
- 地域への愛着
- 職人技へのこだわり
これらの要素は、どんなに施工例が少なくても伝えることができます。むしろ、大手では表現しきれない「温かさ」や「親近感」を演出できるのが、小さな工務店の特権と言えるでしょう。
少ない施工事例を何倍にも活かす「切り取り力」
1つの施工事例から、実は10〜20個の投稿コンテンツを作ることが可能です。これを私は「切り取り力」と呼んでいます。
例えば、1軒の住宅建築から以下のような投稿が作れます:
- 地鎮祭の様子
- 基礎工事の進捗
- 上棟式の模様
- 使用する木材の紹介
- 職人の作業風景
- 設備の取り付け過程
- 内装工事の詳細
- 完成見学会の告知
- お客様の喜びのコメント
- 引き渡し式の感動
このように考えると、たった1件の施工でも2〜3ヶ月分の投稿コンテンツを作ることができます。重要なのは「1つの事例をいかに多角的に見せるか」という視点なのです。

映えるSNS投稿アイデア【実績が少なくてもOK】
ここからは、施工実績が少ない工務店でも今すぐ実践できる、具体的な投稿アイデアを7つご紹介します。どれも特別な技術や高額な機材は不要で、スマホ1台あれば実現可能なものばかりです。
アイデア①:設計段階の図面や3Dパースを使う
完成した建物の写真がなくても、設計図面や3Dパースは立派なコンテンツになります。特に、お客様との打ち合わせ風景や、図面に込めた想いを語る投稿は非常に効果的です。
私が知っているある工務店では、手描きの間取り図を撮影し、「お客様のライフスタイルに合わせて、ここをこう変更しました」という解説付きで投稿したところ、「こんなに丁寧に考えてくれるんですね」というコメントが多数寄せられました。
パースと完成写真を並べることで将来への期待感を伝える
もし過去の施工例が1〜2件でもあれば、その時のパース(予想図)と完成写真を並べて投稿してみましょう。「想像していた通りに仕上がりました!」「お客様の夢が形になった瞬間です」といったコメントを添えることで、まだ家を建てていない見込み客に対して「この工務店なら安心」という印象を与えることができます。
投稿のコツ:パースの段階では「こんな素敵なお家になる予定です♪」、完成時には「パース通りの美しい仕上がりになりました!」というように、時系列で投稿することで、フォロワーに「物語」として楽しんでもらえます。
アイデア②:職人・スタッフ紹介で「安心感」を出す
建物よりも「人」にフォーカスした投稿は、施工実績の少なさをカバーする強力な武器になります。「この人たちが作ってくれるなら安心」という信頼感を醸成できるからです。
- 職人歴○年のベテラン大工の紹介
- 若手職人の成長ストーリー
- 代表の建築への想いやきっかけ
- スタッフの趣味や人柄が見える日常
- チームワークの良さが伝わる現場風景
とある事例では、入社1年目の若い職人さんが先輩に指導を受けている様子を投稿したところ、「教育がしっかりしている会社なんですね」「安心して任せられそう」というコメントが多数寄せられ、実際に問い合わせにつながったケースもあります。
仕事風景や想い、道具へのこだわりも映える
職人さんが使っている道具や、仕事に対する想いを紹介する投稿も効果的です。例えば:
- 「30年愛用している鉋(かんな)です。この道具で美しい仕上がりを実現します」
- 「朝の現場確認は欠かしません。安全第一で今日も頑張ります」
- 「お客様の笑顔が見たくて、細部まで手を抜きません」
職人の技術力やプロ意識が伝わる投稿は、完成写真がなくても十分に魅力的なコンテンツになります。特に、手作業の様子や道具の手入れ風景などは、機械化が進む現代において「職人らしさ」を強く印象付けることができます。
アイデア③:素材や部材の紹介
使用する木材、断熱材、塗料、設備機器などの素材紹介は、専門性をアピールしながら教育的価値も提供できる優秀なコンテンツです。
実際に、ある工務店では地元産の杉材を紹介する投稿で「この木材の特徴」「なぜ選んだのか」「どんな効果があるのか」を詳しく説明したところ、多くのフォロワーから「勉強になりました」「こだわりが伝わってきます」といった反応をもらい、問い合わせ増加につながりました。
https://marklis.com/small-komuten-shukyaku/
木材・塗装・断熱材などの紹介は「プロっぽさ」を演出できる
素材紹介のポイントは、単に商品名を紹介するだけでなく、「なぜその素材を選ぶのか」という理由まで含めて説明することです。
例文:「今回使用するのは地元○○産の無垢杉材です。この木材は調湿効果が高く、一年を通じて快適な湿度を保ってくれます。また、年月と共に風合いが深まり、住むほどに愛着が湧く素材なんです。少し費用は上がりますが、30年後のお客様の笑顔を想像すると、絶対に妥協できない部分ですね。」
このような投稿は、お客様にとって「教育的価値」があるため、保存されやすく、シェアもされやすい特徴があります。結果として、リーチが拡大し、新規フォロワーの獲得にもつながります。
アイデア④:お客様の声や手書きアンケートを投稿
施工実績が少なくても、これまでに関わったお客様からの声は貴重な財産です。第三者からの評価ほど信頼性の高い情報はありません。
特に手書きのアンケートやお礼の手紙は、デジタル時代だからこそ温かみが伝わり、多くの人の心に響きます。私が見てきた中でも、手書きのお客様アンケートを投稿した工務店は、コメント数が通常の3〜5倍になることが珍しくありません。
顔出しNGでも信頼感が伝わる方法
お客様の中には、顔出しやフルネームでの紹介を希望されない方も多いでしょう。そんな場合でも、信頼感を伝える方法はたくさんあります:
- イニシャルや「○○様」での紹介
- 後ろ姿や手元だけの写真
- 手書きアンケートの文字部分のみ
- お客様が描いた間取り図やイラスト
- 完成した家での生活の様子(人物を特定できない範囲で)
大切なのは「リアルな声」が伝わることです。たとえ匿名でも、具体的なエピソードや嬉しかったポイントが書かれていれば、見る人にとって十分な判断材料になります。
アイデア⑤:工事のBefore/Afterを詳細に伝える
リフォーム案件がある場合は、Before/Afterの変化を詳細に伝える投稿が非常に効果的です。新築だけでなく、小さな修繕工事や部分的な改修でも十分にコンテンツになります。
例えば、古い和室を洋室に変える工事、キッチンの交換、外壁の塗り替えなど、どんな小さな工事でも「変化」があれば、それは価値のあるコンテンツです。
「ここがどう変わったか」を説明するだけでも映える
Before/After写真に加えて、「なぜ変更したのか」「どんな工夫をしたのか」「お客様の反応はどうだったか」といったストーリーを加えることで、単なる写真投稿が感動的なコンテンツに変わります。
投稿例:「築40年の和室を、お孫さんが遊べる明るい洋室に改装しました。畳をフローリングに変更し、押入れをクローゼットに。『孫が喜んで遊びに来てくれるようになった』とお客様も大満足です。古い家も、ちょっとした工夫で生まれ変わるんですね。」
このような投稿は、同じような悩みを抱えている潜在顧客に「うちも相談してみようかな」と思わせる効果があります。特に、費用感や工期についても触れると、より具体的な検討材料を提供できます。
アイデア⑥:地域活動や日常の様子を発信
工務店の強みの一つは「地域密着」です。地域のお祭りへの参加、清掃活動、地元イベントのサポートなど、地域との関わりを積極的に発信することで親近感と信頼感を醸成できます。
私が知っているある工務店では、毎月第3土曜日に地域の公園清掃に参加し、その様子を投稿しています。「今月も地域の皆さんと一緒に清掃活動に参加しました。きれいな街づくりも、私たちの大切な仕事の一つです」というメッセージと共に投稿すると、地域住民から多くの「いいね」や「ありがとうございます」のコメントが寄せられます。
地域密着をアピールすることで信頼アップ
地域密着をアピールすることで得られる効果は以下の通りです:
- 地域住民からの親近感と信頼感の向上
- 「何かあったときにすぐ駆けつけてくれそう」という安心感
- 地域の口コミネットワークでの評判向上
- 「地元を大切にする会社」というブランドイメージの構築
- 大手住宅メーカーにはない「温かさ」の演出
また、地域の季節行事(桜の開花、お祭り、雪景色など)と絡めた投稿も効果的です。「今年も桜が咲きました。○○地区で建築中の現場からの眺めも最高です」といった投稿は、地域愛が伝わり、フォロワーとの距離を縮めることができます。
アイデア⑦:自社の理念や代表メッセージを丁寧に伝える
創業の想い、家づくりへの理念、お客様への約束などを丁寧に言語化して投稿することは、施工実績以上にお客様の心に響く場合があります。
特に、代表自らが顔を出して想いを語る動画投稿は、大きな反響を呼ぶことが多いです。ある工務店では、代表が「なぜ工務店を始めたのか」を3分の動画で語ったところ、多くのシェアとコメントが寄せられ、翌月の問い合わせが過去最高になったという事例もあります。
熱意が伝わると投稿が共感を呼ぶ
理念やメッセージを伝える際のポイントは、「なぜその想いを持つようになったのか」という背景も含めて話すことです。単に「お客様第一」と言うだけでなく、その理念が生まれたきっかけやエピソードを交えることで、より深い共感を得られます。
効果的なメッセージ例:「私が工務店を始めたのは、20年前に自分の家を建てたときの経験がきっかけでした。担当者が途中で変わり、約束が守られず、とても不安な思いをしました。『こんな想いをするお客様を一人でも減らしたい』その想いで今日まで続けています。小さな工務店だからこそ、最初から最後まで私が責任を持ちます。」
このような投稿は、見る人の心に強く残り、「この人になら任せられる」という信頼感を醸成します。また、同じような経験をした人からの共感コメントも多く寄せられ、エンゲージメントの向上にも寄与します。

投稿を映えさせる撮影&編集テクニック
どんなに良いコンテンツでも、写真や動画の品質が悪いと魅力が半減してしまいます。ここでは、スマホでも実践できる撮影と編集のテクニックをご紹介します。
撮影時の基本:自然光・水平・背景に注意
プロのような写真を撮るために、まず押さえておきたい基本は以下の3つです:
- 自然光を活用する:室内撮影でも窓際の自然光を使うと、色が自然で美しく写ります
- 水平を意識する:建物や床のラインが傾いていると違和感があります。スマホのグリッド機能を活用しましょう
- 背景を整理する:主役を引き立てるため、余計なものが写り込まないよう気をつけます
実際に、ある工務店では撮影前に現場を5分程度片付けるだけで、投稿写真のクオリティが劇的に向上し、「いいね」の数が平均で2倍になったという事例があります。
また、時間帯も重要です。朝の9時〜11時、午後の2時〜4時頃の自然光が最も美しく、建物の質感や色合いを正確に表現できます。逆に、真昼の直射日光や夕方の黄色い光は、色味が不自然になりがちなので注意が必要です。
スマホでも十分!簡単に映える編集アプリ
撮影した写真を簡単に編集できるアプリを活用することで、プロが撮影したかのような仕上がりにすることができます。
おすすめのアプリと、それぞれの特徴をご紹介します:
- VSCO:フィルター機能が豊富で、建築写真に適したトーンに調整可能
- Lightroom Mobile:プロ仕様の編集が可能で、明るさや色合いの細かい調整ができる
- Snapseed:Googleが提供する無料アプリで、直感的な操作で高品質な編集が可能
- PicsArt:テキスト挿入や装飾機能が豊富で、情報を追加したい投稿に最適
編集のコツ:やりすぎは禁物です。明るさを10〜20%上げる、コントラストを少し強くする、彩度をわずかに上げる程度に留めましょう。自然な仕上がりを心がけることで、見る人に好印象を与えられます。
とある事例では、同じ現場写真でも編集前と編集後で反応が3倍違ったケースもあります。ただし、実際の仕上がりと大きく異なる加工は信頼を損なう可能性があるため、あくまで「見栄えを良くする」程度に留めることが重要です。
CanvaやCapCutで作る統一感のあるデザイン
SNSアカウント全体の統一感を出すために、デザインツールの活用は欠かせません。統一感のあるデザインは、プロフェッショナルな印象を与え、信頼度向上に直結します。
Canvaの活用法:
- 会社ロゴを入れたテンプレートを作成
- 統一されたフォントとカラーパレットの使用
- Before/After比較用のテンプレート作成
- スタッフ紹介用のフォーマット統一
- 素材紹介用の説明パネル作成
CapCutでの動画編集:
- 工事進捗のタイムラプス動画作成
- 職人インタビューの簡単な編集
- BGMとテロップを入れた紹介動画
- オープニング・エンディングの統一
私が知っている工務店では、Canvaで作った統一デザインテンプレートを使い始めてから、「プロっぽくなった」「見やすくなった」というコメントが増え、フォロワー数も月平均50%の成長を続けているという事例もあります。
投稿アイデアを量産するための運用の工夫
継続的にSNS投稿を行うためには、システマチックな運用体制を構築することが重要です。個人の感覚に頼った運用では、必ず息切れしてしまいます。
投稿テーマをカテゴリに分ける(例:現場紹介/スタッフ紹介/素材紹介 など)
投稿内容をカテゴリ分けすることで、ネタ切れを防ぎ、計画的な投稿が可能になります。以下のようなカテゴリ分けがおすすめです:
- 月曜日:現場レポート(工事進捗、新しい現場の紹介など)
- 火曜日:スタッフ・職人紹介(人柄、技術、エピソードなど)
- 水曜日:素材・設備紹介(こだわりの材料、新商品情報など)
- 木曜日:お客様の声(アンケート、完成後の様子など)
- 金曜日:豆知識・Tips(住まいの知識、メンテナンス方法など)
- 土曜日:地域情報・イベント(地域活動、完成見学会など)
- 日曜日:代表メッセージ・理念(想い、業界動向への意見など)
このようにテーマを決めることで、「今日は何を投稿しよう」と悩む時間が大幅に短縮されます。また、フォロワーにとっても「月曜日は現場の様子が見られる」という期待感を持ってもらえます。
運用のコツ:週7日投稿が難しい場合は、週3日(月・水・金など)に絞って確実に継続することを優先しましょう。不定期な投稿よりも、頻度は少なくても規則的な投稿の方が、フォロワーの定着率が高くなります。
週に1回の投稿でも”世界観”を意識する
投稿頻度が少なくても、一貫した「世界観」を演出することで、強い印象をフォロワーに残すことができます。世界観とは、色使い、文体、写真のトーン、メッセージの方向性などを統一することです。
例えば、「温かみのある自然素材を大切にする工務店」という世界観なら:
- 写真は暖色系のトーンで統一
- 文体は親しみやすく、丁寧な関西弁
- 木材や自然素材の質感を強調
- 家族の温かさを感じるエピソードを中心に
- ロゴや装飾は木目調のデザインで統一
一方、「最新技術を活用するスタイリッシュな工務店」なら:
- 写真はクールで現代的なトーン
- 文体はスマートで簡潔
- 最新設備や技術情報を中心に
- 効率性や機能性を強調するメッセージ
- デザインはミニマルで洗練された印象
世界観が一貫していると、少ない投稿でもブランドイメージが確立され、記憶に残りやすくなります。
ストーリーズやリールも併用して露出を増やす
通常の投稿だけでなく、ストーリーズやリール機能を活用することで、より多くの人にリーチすることが可能です。特に、ストーリーズは24時間で消える気軽さがあるため、日常的な投稿に適しています。
ストーリーズの活用例:
- 朝の現場巡回の様子
- 職人さんの昼食風景
- 材料搬入の瞬間
- お客様との打ち合わせ後の感想
- 完成間近の「あと少しで完成です!」報告
リールの活用例:
- 工事の進捗をタイムラプスで紹介
- 職人の技術を短時間で見せる動画
- Before/Afterを劇的に見せる動画
- 「こんな時どうする?」住まいのQ&A動画
- 素材の特徴を実験で証明する動画
ある工務店では、リール投稿を始めてから、通常投稿の10倍以上のリーチを獲得し、新規フォロワーが月間200%増加したという事例もあります。
フォロワーとの関係性を築くコメント・DM対応
SNSは双方向のコミュニケーションツールです。投稿するだけでなく、コメントやDMへの丁寧な対応が信頼関係構築の鍵となります。
コメント対応のポイント:
- できるだけ24時間以内に返信する
- 質問には具体的で親切に回答する
- 感謝の気持ちを必ず表現する
- 名前を呼んで親近感を演出する
- 絵文字を適度に使って親しみやすさを出す
返信例:「○○さん、コメントありがとうございます!その断熱材についてですが、実は…(具体的な説明)…です。もしもっと詳しく知りたいことがあれば、DMでもお気軽にご質問くださいね♪」
私が見てきた中で、コメント対応が特に丁寧な工務店は、SNS経由の問い合わせ率が平均の3倍以上になっています。一つ一つのやり取りが、将来のお客様との関係性を築く貴重な機会だと考えて対応することが重要です。
施工例が少ない時期でも集客につなげるSNS導線
SNSの投稿自体が目的ではありません。最終的には問い合わせや相談につなげる必要があります。ここでは、施工例が少ない段階でも効果的な集客導線の作り方をご説明します。
SNS→ホームページ→問い合わせの流れを設計する
SNSからいきなり問い合わせを求めるのではなく、段階的に信頼を積み重ねていく導線設計が重要です。「知る→興味を持つ→詳しく調べる→検討する→問い合わせる」という段階を意識しましょう。
効果的な導線設計例:
- 第1段階(認知):SNS投稿で存在を知ってもらう
- 第2段階(興味):プロフィールリンクからホームページへ誘導
- 第3段階(検討):ホームページで詳細情報や施工事例を確認
- 第4段階(行動):資料請求や無料相談に申し込み
ホームページには以下の要素を充実させることが重要です:
- 代表者の顔写真と詳しいプロフィール
- 施工事例(少なくても詳細に紹介)
- お客様の声やアンケート結果
- 施工の流れや品質管理について
- よくある質問とその回答
- 無料相談や資料請求の申し込みフォーム
重要なポイント:SNSで興味を持った人がホームページを訪れた時に、「この会社に任せてみたい」と思えるような情報を充実させることが重要です。施工例が少ない場合は、一つ一つの事例を非常に詳しく紹介し、お客様の満足度の高さを強調しましょう。
GoogleビジネスプロフィールやLINE公式アカウントと連携する
SNSだけでなく、複数のオンラインツールを連携させることで、より強固な集客基盤を構築できます。
Googleビジネスプロフィールとの連携効果:
- 地域検索での表示機会増加
- Googleマップでの露出向上
- 口コミ機能での信頼性アップ
- 投稿機能でSNSと同様の情報発信
- 問い合わせやルート案内の簡素化
LINE公式アカウントとの連携効果:
- 気軽なコミュニケーション手段の提供
- リアルタイムでの質問・相談対応
- 見学会やイベント情報の配信
- 個別相談やフォローアップの実施
- 資料や写真の簡単な共有
実際に、SNS投稿にGoogleビジネスプロフィールとLINE公式アカウントのリンクを記載するようにしてから、問い合わせ経路が多様化し、月間の相談件数が40%増加したという事例があります。
連携のコツは、それぞれの特性を活かした役割分担です:
- SNS:認知拡大とブランディング
- Googleビジネスプロフィール:地域密着と信頼性向上
- LINE公式アカウント:個別対応とフォローアップ
- ホームページ:詳細情報と最終的な決断支援
投稿ごとに目的(ブランディング/集客/教育)を決める
すべての投稿に明確な目的を設定することで、より戦略的で効果的なSNS運用が可能になります。目的を意識することで、投稿の質も向上し、成果も測定しやすくなります。
ブランディング目的の投稿例:
- 代表の理念や想いを語る投稿
- 職人の技術やこだわりを紹介する投稿
- 地域活動への参加報告
- 会社の歴史や成り立ちを紹介
集客目的の投稿例:
- 完成見学会の告知
- 無料相談会の案内
- お客様の満足度や喜びの声
- 「お気軽にご相談ください」というCTA付き投稿
教育目的の投稿例:
- 住宅の基礎知識や豆知識
- 素材の特徴や選び方の解説
- メンテナンス方法の紹介
- 建築業界のトレンド解説
バランスの目安:ブランディング40%、教育40%、集客20%程度の割合で投稿することで、フォロワーに有益な情報を提供しながら、適度に集客につなげることができます。集客色が強すぎると敬遠される可能性があるため注意が必要です。
目的を明確にすることで、投稿の成果も測定しやすくなります。ブランディング投稿なら「いいね」や「保存」の数、教育投稿なら「シェア」や「コメント」の数、集客投稿なら「プロフィールクリック」や「問い合わせ」の数を重要な指標として追跡しましょう。
https://marklis.com/koumuten-sns-meo-tips/
よくある質問(Q&A)
Q1: 施工写真が1件しかありません。どう活用すればよい?
A1: 1件の施工事例でも、工事の各段階(着工前→基礎→骨組み→内装→完成)に分けて投稿すれば、5〜10回分のコンテンツになります。さらに、使用した素材の紹介、職人さんの作業風景、お客様の喜びの声なども加えれば、1ヶ月以上の投稿ネタを作ることができます。重要なのは、一つの事例をいかに多角的に見せるかという視点です。
Q2: 投稿する時間帯はいつが良いですか?
A2: 一般的には、朝7〜8時、昼12〜13時、夜19〜21時がSNSの利用者が多い時間帯とされています。ただし、工務店のターゲット層を考えると、土日の午前中(9〜11時)や平日の夜(19〜20時)が効果的な場合が多いです。まずは複数の時間帯で試してみて、自社のフォロワーの反応が良い時間を見つけることをおすすめします。
Q3: 投稿しても反応が少ないのですが、どう改善すべき?
A3: 反応が少ない主な原因は以下の通りです:①投稿内容が一方的で、読者にとって有益でない②写真の質が低い③ハッシュタグの選定が不適切④投稿時間が悪い⑤継続期間が短い。改善策としては、まず読者目線で「この投稿は自分にとって有益か?」を考え直すことから始めましょう。また、地域に特化したハッシュタグ(#○○市工務店、#○○県注文住宅など)を活用することで、ターゲットに届きやすくなります。
Q4: ストーリーズとリールは使ったほうが良い?
A4: はい、積極的に活用することをおすすめします。ストーリーズは日常的な投稿に最適で、フォロワーとの距離を縮める効果があります。リールは拡散力が高く、新規フォロワー獲得に効果的です。通常投稿、ストーリーズ、リールをバランスよく使い分けることで、より多くの人にリーチできます。ただし、無理に毎日投稿する必要はありません。質を重視して、週に2〜3回の投稿から始めることをおすすめします。
Q5: 他社の施工写真を使ってもいいですか?
A5: 絶対に避けてください。他社の施工写真を無断で使用することは著作権侵害にあたる可能性があります。また、後でトラブルになったり、信頼を失ったりするリスクもあります。自社の実力を正直に伝えることが、長期的な信頼関係構築につながります。施工例が少ない場合は、この記事で紹介したような代替コンテンツ(設計図面、素材紹介、スタッフ紹介など)を活用しましょう。素材メーカーの公式画像や、許可を得た画像のみを使用するようにしてください。
Q6: フォロワーが増えません。どうすれば良いでしょうか?
A6: フォロワー数よりもエンゲージメント率(いいね、コメント、保存の率)を重視しましょう。100人の熱心なフォロワーは、1000人の無関心なフォロワーよりも価値があります。フォロワーを増やすコツは:①地域に特化したハッシュタグの活用②他の地域企業や関連業界の投稿にいいねやコメント③地域イベントでの積極的なSNS活用④お客様に「良かったらフォローしてください」と自然にお願いする、などがあります。
Q7: 競合他社もSNSをやっているので不安です。
A7: 競合がいることは良いことです。それだけ市場にニーズがあるということですから。大切なのは他社との差別化を図ることです。同じような投稿をするのではなく、自社独自の強み(代表の人柄、職人の技術、地域への想い、独自の施工方法など)を前面に出しましょう。お客様は「どの工務店でも同じ」ではなく、「この会社だからお願いしたい」と思える理由を探しています。
まとめ
自社施工例が少ない工務店でも、アイデアと工夫次第で魅力的なSNS投稿を作ることは十分可能です。重要なのは、「施工写真がないから投稿できない」という固定観念を捨て、「伝えたいことはたくさんある」という視点に切り替えることです。
この記事でご紹介した7つのアイデア(設計図面の活用、スタッフ紹介、素材紹介、お客様の声、Before/After、地域活動、理念の発信)は、どれも特別な技術や高額な機材を必要としません。大切なのは継続することと、読者にとって価値のある情報を提供し続けることです。
また、SNSは「未来の施工例を生むための種まき」でもあります。今日の投稿が来月の問い合わせにつながり、半年後の施工契約につながり、1年後には豊富な施工事例を投稿できるようになるかもしれません。
最後に大切なことをお伝えします。SNSでの成功に「魔法の方法」はありません。地道な継続と、お客様への真摯な想いが最も重要な要素です。完璧を求めすぎず、まずは今日から一歩を踏み出してみてください。
小さな工務店だからこそ伝えられる温かさ、お客様一人ひとりを大切にする姿勢、地域に根ざした信頼関係。これらはどんな大手企業も真似できない、あなたの会社だけの宝物です。
SNSを通じて、その宝物を一人でも多くの方に伝えていけば、きっと素晴らしい出会いと成果が待っています。継続と工夫こそが、施工実績の少なさを補い、やがては豊富な実績へとつながる成功への近道なのです。